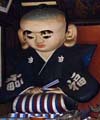|
伊吹山は古くから、人々との関わり合いが深い山で、「古事記」では倭建命・「日本書紀」では大和武尊の記述がある。 ■作成:筒井杏正・幸田正榮 |
||
|
■日本最古の書物「古事記&日本書紀」に登場
|
||||
|
時代区分
|
書物名
|
伊吹山との関連
|
||
|
奈良初期
|
古事記
712年 |
|
||
|
日本書紀
720年 |
|
|||
|
伊吹山が、当時多くの人がたしなんだ、和歌によく登場するようになったのは、都が奈良からに遷都した平安時代(794〜1086)及びそれ以降で各種記録がある。 都が京都に移ると、「伊吹山」は都により近い存在となり、多くの人々が和歌を作るようになった。歌を見ると当時の女官、殿上人達の確執などがうかがえて面白い。 |
||||
|
高級ブランド品「伊吹もぐさ」を題材に歌った「和歌」
|
|
| 特に、伊吹山自生のオオヨモギは、お灸の材料として高級ブランド品として全国に知られていました。 | |
| <恋歌の題材=伊吹のさしも草> その特徴として、一度火をつけると消えにくく、長時間熱さが持続するということから、愛の燃ゆる想いを表す、「恋」を主題とする和歌の絶好の題材となりました。それは、主として女官・殿上人達の和歌作成の題材となったようです。 ※伊吹山の他「さしもぐさ」は下野(栃木県)の「しめじがはら」の「ヨモギ」を指すという説もある。【関連記事】
|
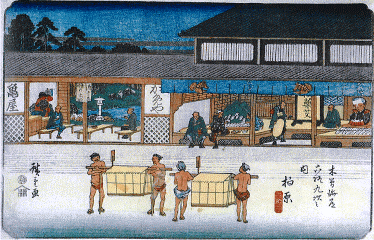 ← 店頭の大きな福助のぬいぐるみは、今もこの老舗の看板と なっている |
先頭ページのへ
先頭ページのへ
|
<その他伊吹のさしも草を詠んだ和歌>
|
|||||||||||
|
平安中期
|
春きぬと 伊吹の山邊にも またしかりける 鶯の声 (古今和歌集六帖 第二764 喜撰法師) あぢきなや 伊吹の山の さしも草 おのが思ひに 身をこがしつつ (古今和歌六帖・第六・3586 藤原行成) さしも草 もゆる伊吹の 山の端の いつともわからぬ 思ひなりけり (古今集六帖 藤原頼氏) さしもやは みにしむいろも いぶきやま はげしくおろす みねのあきかぜ (古今集六帖 藤原俊成女) 契りけん 心からこそ さしも草 をのか思ひに もえわたりけれ (古今和歌集六帖) 「加茂真淵全集 27巻」 なをさりに いふきの山の さしも草 さしも思わぬ ことにやはあらぬ (古今和歌集六帖) 「加茂真淵全集 27巻」 秋をやく 色にぞ見ゆる 伊吹山 もえてひさしき 下の思ひも (藤原定家 和漢朗詠集) 1018年 |
||||||||||
|
古今和歌集 平安後期 |
|
||||||||||
先頭ページのへ
|
鎌倉時代
1185年 〜 1333年 |
1201〜
1210年 拾遺愚草 藤原定家 |
<藤原定家が詠んだ歌>
拾遺愚草 中 藤原定家全歌集上 1873番 色にいでて うつろう春を とまれとも えやは伊吹の 山ぶきの花 【歌意】 はっきりと様子に現れて移ろっていく春を、山吹の花は「止まれ」とどうして言うことが出来ようか、なぜといって山吹はくちなし色だから。 拾遺愚草 上 藤原定家全歌集上 1157番 しられじな 霞のしたに こがれつつ 君に伊吹の さしもしのぶと 【歌意】 私が霞の下にむせびながら、このように恋心を打明けもしないで忍んでいると、あの人には知られないだろうか 和泉式部
今日もまた このように辛いことを あなたは言うのですか。 それならば 私だけが 伊吹のさしも草のように 恋の思いで燃え続けるのでしょうか。 和泉式部は、恋多き女性と言われ、冷泉( れいぜい)天皇の子・為尊( ためたか )親王やその弟、敦道( あつみち )親王との恋の顛末はよく知られています。 この歌は、恋する女の激しい情念と言おうか、少し怖さえ覚えてしまいます。ただ、誰にあてて詠ったかは定かではありません。 |
|
<その他 鎌倉時代と室町時代 伊吹山を詠んだ の和歌>
|
||
|
鎌倉初期
|
古今和歌集
詠み人知らず |
さえまさる 伊吹が嶽の 山おろしに こほりはてたる 余吾の内海 衣笠内大臣(衣笠家良) 1192〜1264 【歌意】寒さが一層厳しくなる、伊吹の嶽のやまおろしで、凍ってしまった余呉の内海 「夫木和歌抄 巻第二十一嵩」 たまかつら 伊吹の山の 秋の露 誰おもかけの 末虫をこえ 順徳院(1197〜1242) 後鳥羽天皇の第三皇子、84代天皇 【歌意】鳴き弱った垣根の虫も秋を止められないように、わたしもあなたが行くのを止められない さしも草 さしもしのびぬ 中ならば 思ひありとも 言はましものを (正治初度百首・1175、藤原俊成) 1200年 忘れじと ともに伊吹の さしも草 さしも契りし 言の葉ぞかし (万代集・恋四・2385、北条重時) 1248年 |
|
室 町
南北朝 |
千載集
|
さしも草 さしもひまなき 五月雨に 伊吹の岳の なほや燃ゆらん (新拾遺集・夏・269、藤原家良) 1364年 |
|
<江戸時代は、俳句の題材に・・・>
|
||||
|
時代区分
|
書物名
|
伊吹山との関連
|
||
|
江戸中期
1669年 |
松尾芭蕉
奥のほそ道 「後の旅集」 「笈日記」 元禄四年 1961年 |
|
||
先頭ページのへ
|
「芭蕉の句」を気象学的に見て科学的に分析した寺田寅彦(随筆)
|
||||||||
|
大正13
1924年 2月 |
寺田寅彦
随筆集 第三巻 「俳句と芸術」 潮 音 |
|
||||||
|
明治・大正・昭和時代 伊吹山を詠んだ俳句集
|
||
|
江戸中期
(元禄年間) |
芭蕉の俳人
|
中川乙由(伊勢山田の人。通称喜右衛門。別号麦林舎) 秋はあの 伊吹にありて 蘇鉄山 |
|
江戸後期
明 治 |
政治家
|
原敬(1856〜1921) 雪晴や 目鼻書きたき 伊吹山 |
|
明 治
大 正 昭 和 平 成 |
現代
俳句協会 |
森 澄雄(1919〜2010) 秋澄むや 湖のひがしに もぐさ山 秋風の 吹きわたりゐる 伊吹山 まぼろしの 鷹をえがくや 奥伊吹 をりをりや 簾のそとの 伊吹山 秋風の 吹きあたりゐる 伊吹山 |
|
平井照敏
の俳句(六) |
平井 照敏(1931〜2003) 雪解けの かたまりとなり 伊吹山 (1974) |
|
|
茨木和生
|
茨木和生(1939〜 ) 諸子舟 伊吹の晴に 出しにけり |
|
先頭ページのへ
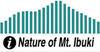
伊吹山と植物と地質と文学